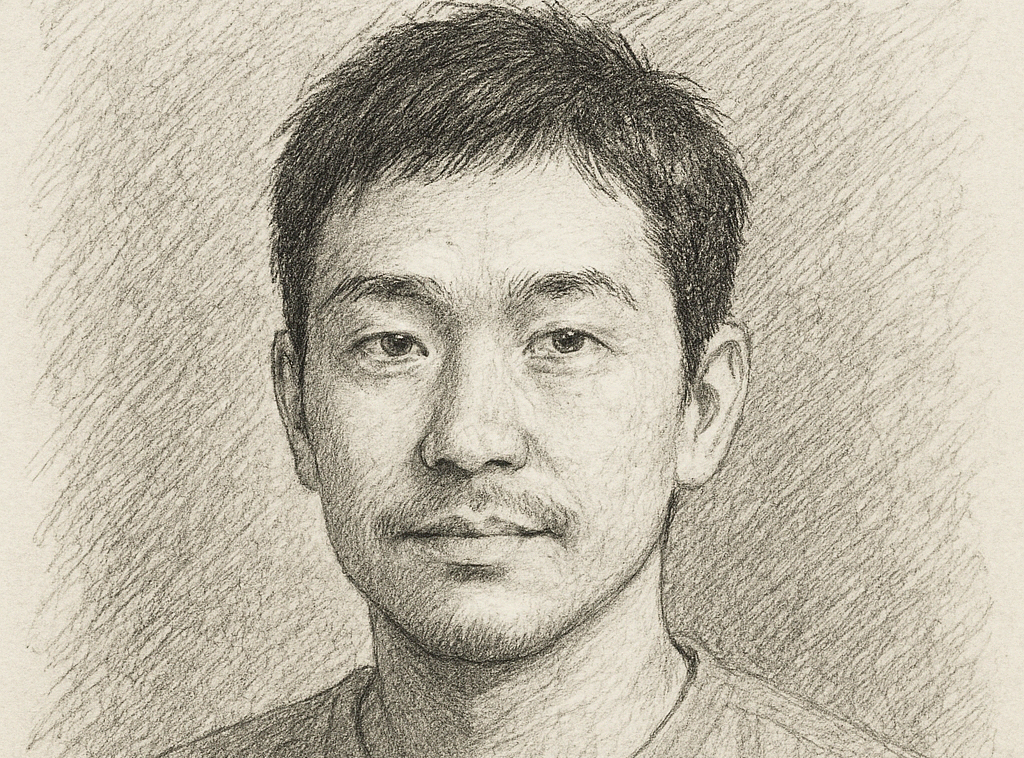屋根裏換気扇のデメリットとは?知っておくべき注意点と対策方法
近年、住宅の快適性を高めるために「屋根裏換気扇」の設置を検討する方が増えています。屋根裏換気扇は熱や湿気の排出に効果的ですが、設置する前に知っておくべきデメリットもあります。
この記事では、屋根裏換気扇のデメリットや注意点を詳しく解説し、メリットを最大限に活かすための対策方法についてもご紹介します。住宅環境の改善を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

「まずは住宅展示場へ行こう」と思っている方はちょっと待って!
まずは自宅でしっかりと情報を集めてから住宅展示場に行かないと、営業マンの話を一方的に聞いて、大した収穫もなく帰ることになります。
「タウンライフ家づくり」は、自宅にいながら全国1180社以上のハウスメーカーや工務店の中から、提案を受けることができるサービス!
他にも資料を一括で請求できるサービスはありますが、タウンライフ家づくりが凄いのは、資料だけでなく「間取り提案」「詳細な見積もり」が複数社から無料で貰えます!
\簡単・たったの3分/
無料の間取り・見積もり提案はコチラから >
屋根裏換気扇とは何か?そのデメリットを知る前に
屋根裏換気扇は、屋根裏に溜まった熱や湿気を外に排出するための装置です。通常の換気扇と異なり、屋根裏専用に設計されています。設置することで湿気やカビの発生を防ぎ、夏場の暑さを軽減できるというメリットがあります。
しかし、多くのメリットがある一方で、屋根裏換気扇にはいくつかのデメリットも存在します。設置を検討する前に、これらのデメリットをしっかりと理解しておくことが大切です。
屋根裏換気扇の主なデメリット
初期費用が高額になる
屋根裏換気扇の最も大きなデメリットの一つは、初期費用が高額になることです。換気扇本体の価格に加えて、設置工事費用も必要となります。
屋根裏換気扇の設置工事費用は一般的に5万円から15万円程度かかります。工事内容によっては、さらに費用が高くなることもあります。特に、電気配線の新設や屋根に穴を開ける作業が必要な場合は、専門業者への依頼が必須となり、その分のコストが上乗せされます。
このように、屋根裏換気扇を設置するには決して安くない初期投資が必要になるため、予算の制約がある場合は慎重に検討する必要があります。
メンテナンスの手間とコスト
屋根裏換気扇のもう一つの大きなデメリットは、定期的なメンテナンスが必要なことです。
屋根裏はホコリや汚れが溜まりやすい場所です。換気扇のフィルターやファンにホコリが蓄積すると、換気能力が低下するだけでなく、モーターに余計な負担がかかり、故障の原因にもなります。
定期的な清掃や点検を怠ると、換気効率が落ちるだけでなく、最悪の場合は火災のリスクも高まります。特に屋根裏は高温になりやすい場所なので、ホコリが堆積した状態で換気扇が過熱すると危険です。
メンテナンスは少なくとも年に1〜2回は必要で、場合によっては専門業者に依頼する必要があります。このメンテナンスにかかる手間とコストも、屋根裏換気扇のデメリットと言えるでしょう。
耐久性と寿命の問題
屋根裏換気扇は一般的に10〜15年程度の寿命があるとされていますが、使用環境やメンテナンス状況によっては、それよりも早く故障することがあります。
屋根裏は温度変化が激しく、湿気も多い環境です。このような過酷な条件下で常時稼働させるため、一般的な換気扇よりも負担が大きくなります。特に低品質の換気扇を選んだ場合、5〜7年程度で故障することもあるのです。
換気扇が故障した場合は交換が必要になりますが、屋根裏での作業は専門知識が必要なため、自分で対応することは難しく、再び工事費用がかかることになります。
電気代の負担
屋根裏換気扇のデメリットとして、電気代の負担も考慮する必要があります。
屋根裏換気扇は通常24時間稼働させることが推奨されています。消費電力は機種によって異なりますが、一般的な換気扇の場合、1ヶ月の電気代は数百円程度かかります。
例えば、消費電力が5Wの換気扇を24時間稼働させた場合、1ヶ月の電気代は約100円程度です。これだけなら大きな負担にはなりませんが、長期間にわたって考えると、決して無視できない金額になります。
また、ホコリや汚れが溜まると余計な電力を消費するため、定期的な清掃をしないと電気代が増加する可能性もあります。
騒音問題
屋根裏換気扇は稼働時に音が発生します。静音設計の製品もありますが、完全に無音で動作するわけではありません。
特に寝室やリビングの真上に設置した場合、モーター音や風切り音が気になることがあります。夜間、静かな環境では特に音が目立ちやすく、睡眠の妨げになる可能性もあるのです。
また、換気扇が古くなったり、メンテナンス不足だったりすると、異音が発生することもあります。このような騒音問題も屋根裏換気扇のデメリットの一つと言えるでしょう。
冬場の冷気流入による問題
温度管理の難しさ
屋根裏換気扇のデメリットとして見逃せないのが、冬場の冷気流入問題です。
換気扇によって屋根裏の空気が外に排出されると、その分外気が流入します。夏場はこれが室温の低下につながりますが、冬場は逆に冷たい外気が入り込むことになります。
屋根裏の断熱性能が低い場合、この冷気が居住空間に影響を与え、室温が下がる原因になることがあります。その結果、暖房効率が悪くなり、暖房費が増加する可能性もあるのです。
断熱対策の必要性
冬場の冷気流入を防ぐためには、適切な断熱対策が必要です。屋根裏換気扇を設置する際は、同時に断熱材の増設や隙間の封鎖など、断熱性能を高める工事も検討すべきでしょう。
しかし、このような追加工事によってさらに費用がかさむことになります。屋根裏換気扇のデメリットを考える際は、このような追加コストも考慮に入れる必要があります。
設置場所の制約
理想的な設置場所の確保が難しい
屋根裏換気扇の効果を最大限に発揮するためには、適切な設置場所を選ぶことが重要です。しかし、既存の住宅では理想的な設置場所の確保が難しいことがあります。
屋根裏換気扇は、熱や湿気が溜まりやすい場所に設置するのが効果的です。また、給気口との位置関係も重要で、空気の流れを考慮した配置が必要になります。
しかし、屋根の構造や梁の位置、電源の確保など、様々な制約によって理想的な設置場所に換気扇を取り付けられないケースも少なくありません。このような設置場所の制約も、屋根裏換気扇のデメリットの一つと言えるでしょう。
住宅構造との相性
住宅の構造によっては、屋根裏換気扇の効果が十分に発揮されないことがあります。特に複雑な形状の屋根や、小さな屋根裏空間の場合は、空気の流れが悪くなり、換気効率が低下する可能性があります。
また、古い住宅では電気配線の問題や屋根材の劣化など、設置工事に支障をきたす要因が多いこともあります。このような住宅構造との相性も、屋根裏換気扇のデメリットとして考慮すべき点です。
DIY設置の難しさ
専門知識と資格の必要性
屋根裏換気扇の設置をDIYで行うことは、一見簡単に思えるかもしれませんが、実際には多くの専門知識と技術が必要です。
特に電気工事が伴う場合は、電気工事士の資格が必要になります。無資格でこのような工事を行うと法律違反となり、罰則の対象になることもあるので注意が必要です。
また、屋根に穴を開ける作業では、防水処理の知識も求められます。不適切な施工をすると雨漏りの原因になり、建物に大きなダメージを与える恐れがあります。
失敗のリスクと責任
DIYで設置に失敗した場合、修理や再工事に大きなコストがかかる可能性があります。また、不適切な設置が原因で火災や雨漏りなどの事故が起きた場合、責任はすべて自分自身に及びます。
保険の適用も難しくなる可能性があるため、DIY設置のリスクは決して小さくありません。このように、専門知識を要する屋根裏換気扇の設置は、DIYには向かないという大きなデメリットがあります。
屋根裏換気扇のデメリットを軽減する方法
適切な製品選びのポイント
屋根裏換気扇のデメリットを軽減するためには、まず適切な製品選びが重要です。以下のポイントを考慮して選びましょう。
消費電力が少なく、静音設計の製品を選ぶ
耐久性が高く、高温環境に対応できる製品を選ぶ
メンテナンスがしやすい構造の製品を選ぶ
温度センサーなど、効率的な運転ができる機能を持つ製品を選ぶ
これらのポイントを押さえた製品を選ぶことで、電気代や騒音問題、メンテナンスの手間などのデメリットを軽減できます。
効果的な設置場所と方法
屋根裏換気扇の効果を最大限に発揮するためには、設置場所と方法にも注意が必要です。
熱や湿気が溜まりやすい場所に設置するのはもちろん、給気口との位置関係も重要です。空気の流れを考慮した配置により、換気効率を高めることができます。
また、振動や音を抑えるためのマウントや、防水・防塵対策なども忘れずに行いましょう。これらの工夫により、騒音問題や耐久性の問題といったデメリットを軽減できます。
定期的なメンテナンスの重要性
屋根裏換気扇のデメリットを軽減するためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。
少なくとも年に1〜2回は、フィルターやファンの清掃を行いましょう。ホコリや汚れが溜まると換気効率が落ちるだけでなく、故障や火災のリスクも高まります。
また、モーターや電気配線の点検も忘れずに行いましょう。異音や振動が大きくなったら、故障の前兆の可能性があります。早めに専門業者に相談することで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。
屋根裏換気扇の代替案
自然換気システムの活用
屋根裏換気扇のデメリットが気になる場合は、自然換気システムを活用する方法もあります。
軒下の通気口や換気棟、ベンチレーターなどを適切に配置することで、機械的な換気扇を使わなくても、ある程度の換気効果を得ることができます。
自然換気システムなら電気代がかからず、故障の心配もありません。ただし、風の強さや方向に影響されるため、安定した換気効果は期待できないという点は理解しておく必要があります。
調湿材の活用
屋根裏の湿気対策としては、調湿材の活用も効果的です。調湿材は周囲の湿度に応じて湿気を吸収したり放出したりする特性を持ち、屋根裏の湿度を一定に保つのに役立ちます。
調湿材は設置が簡単で、電気代もかからないというメリットがあります。屋根裏換気扇と併用することで、より効果的な湿気対策が可能になります。
調湿材の価格は材質や設置面積によって異なりますが、1個あたり約2,500円程度です(1坪あたり12個〜16個が設置数の目安)。換気扇よりも初期費用を抑えられる場合もあります。
まとめ:屋根裏換気扇のデメリットを理解した上で検討しよう
屋根裏換気扇には、湿気やカビの発生を防ぎ、室内環境を改善するという大きなメリットがあります。しかし、ここで紹介したように、いくつかのデメリットもあることを忘れてはいけません。
初期費用が高額になる
定期的なメンテナンスが必要
耐久性と寿命の問題がある
電気代の負担がある
騒音問題がある
冬場の冷気流入による問題がある
設置場所に制約がある
DIY設置が難しい
これらのデメリットを理解した上で、自宅の状況や予算に合わせて、屋根裏換気扇の設置を検討しましょう。場合によっては、自然換気システムや調湿材など、他の選択肢を組み合わせることで、より効果的な屋根裏環境の改善が可能になるかもしれません。
大切なのは、メリットだけでなくデメリットもしっかりと理解し、長期的な視点で判断することです。屋根裏換気扇の設置を検討している方は、専門業者に相談して、自宅に最適な換気対策を見つけましょう。
住宅展示場に行こうと思っている方や間取りで悩んでいる方へ

注文住宅を検討している方は、「とりあえず住宅展示場へ行ってみようかな?」という方がほとんどです。
しかし、住宅展示場はオススメしません。理由は下記の3つです。
・グレードの高い住宅展示場のモデルハウスは参考にならない。
・大した収穫もなく、資料だけもらって帰ることになる。
また、ハウスメーカーは決まっているけど、間取りに悩んでいるという方へ。他の会社からも間取り提案を無料で受けられるとしたら、魅力的ではないでしょうか?
そこで、オススメするサービスが「タウンライフ家づくり」です。
「タウンライフ家づくり」は完全無料で資料・間取り提案・見積もりがもらえる

「タウンライフ家づくり」は、自宅にいながら全国のハウスメーカーや工務店から提案を受けることができるサービスです。
他にも資料を一括で請求できるサービスはありますが、タウンライフ家づくりが凄いのは、資料だけでなく「間取り提案」「詳細な見積もり」が無料で貰えることです。
累計利用者数は40万人となり、毎月5,000人以上が利用する人気のサービスとなっています。
\簡単・たったの3分/
無料の間取り・見積もり提案はコチラから >
全国1180社以上の加盟店で希望の会社が見つかる
誰もが知っている大手ハウスメーカー27社に加えて、全国のハウスメーカーや工務店など合わせて1180社以上の登録があります。これだけのハウスメーカーや工務店がタウンライフ家づくりに登録していることで、信頼を集める理由となっています。下記はほんの一例です。

また、アンケート調査では、注文住宅部門で3冠を達成しています。

\簡単・たったの3分/
無料の間取り・見積もり提案はコチラから >
依頼は簡単で最短3分の2ステップ
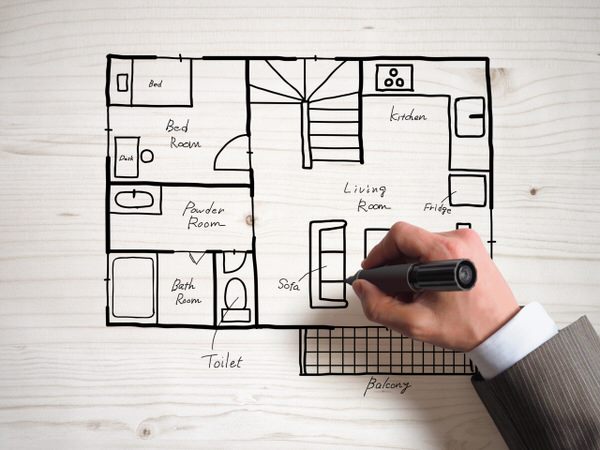
タウンライフ家づくりへの依頼は、とても簡単です。
・希望のハウスメーカー・工務店を選択
\簡単・たったの3分/
無料の間取り・見積もり提案はコチラから >
【PR】
【関連記事はこちら】