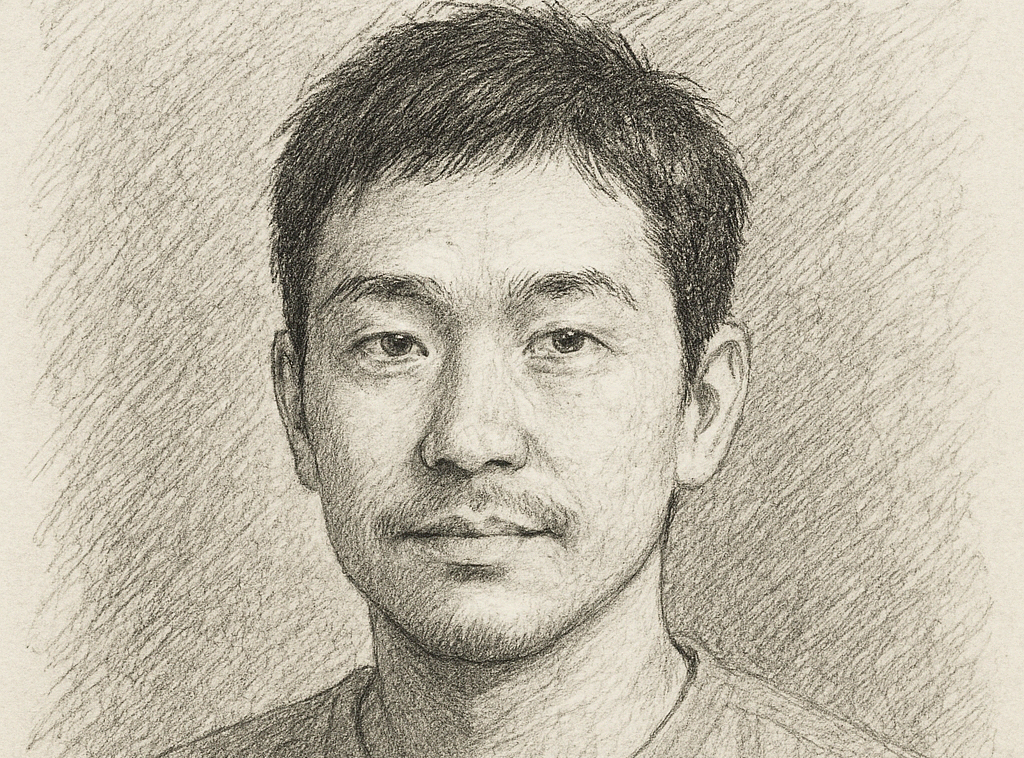ガレージに固定資産税はかかる?種類別の課税対象と回避方法を徹底解説
ガレージを設置したいと考えている方にとって、気になるのが固定資産税の問題です。どのようなガレージに固定資産税がかかるのか、また固定資産税がかからない方法はあるのかなど、多くの疑問をお持ちではないでしょうか。
この記事では、ガレージの種類ごとに固定資産税がかかるケースとかからないケースを詳しく解説します。ガレージを設置する前に、ぜひ参考にしてください。

「まずは住宅展示場へ行こう」と思っている方はちょっと待って!
まずは自宅でしっかりと情報を集めてから住宅展示場に行かないと、営業マンの話を一方的に聞いて、大した収穫もなく帰ることになります。
「タウンライフ家づくり」は、自宅にいながら全国1180社以上のハウスメーカーや工務店の中から、提案を受けることができるサービス!
他にも資料を一括で請求できるサービスはありますが、タウンライフ家づくりが凄いのは、資料だけでなく「間取り提案」「詳細な見積もり」が複数社から無料で貰えます!
\簡単・たったの3分/
無料の間取り・見積もり提案はコチラから >
固定資産税とは何か
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や家屋、償却資産などの固定資産を所有している人に課される地方税です。この税金は地方自治体の重要な財源となっています。
ガレージも一定の条件を満たすと「家屋」として扱われ、固定資産税の課税対象になります。そのため、ガレージを設置する際には、毎年いくらの固定資産税がかかるのかを事前に確認しておくことが大切です。
固定資産税の税額は、固定資産の評価額に1.4%の税率を乗じて計算されます。ガレージの場合、建築費の約60%程度が評価額となることが多いです。例えば100万円でガレージを建てた場合、評価額は約60万円となり、固定資産税は年間約8,400円(60万円×1.4%)となります。
ガレージに固定資産税がかかる条件
ガレージが固定資産税の課税対象となるかどうかは、以下の3つの条件によって決まります。この3つの条件をすべて満たすと、ガレージは「家屋」とみなされ、固定資産税がかかります。
外気分断性があること
外気分断性とは、建物の内部と外部を区別し、外気の影響(風や雨など)から内部を保護する性質を指します。一般的に、3方向以上が壁で囲まれていて屋根がある建物は、外気分断性があると判断されます。
例えば、シャッター付きのガレージは、シャッターを閉めると外部と内部が区別され、外気から内部を保護できるため、外気分断性があると判断されます。
定着性があること
定着性とは、建物が土地に固定されていて、簡単には移動できない性質を指します。基礎工事を行って地面に固定されているガレージは、定着性があると判断されます。
反対に、地面に置いているだけの簡易的な物置などは、定着性がないため固定資産税の課税対象にはなりません。
用途性があること
用途性とは、建物が特定の目的や用途を持っていることを指します。ガレージは車両を保管するという明確な目的があるため、一般的に用途性があると判断されます。
ただし、車両を保管する目的でガレージを作っても、「外気分断性」と「定着性」を満たさなければ、固定資産税はかかりません。
固定資産税がかかるガレージの種類
3つの条件をすべて満たすガレージには、固定資産税がかかります。具体的に、どのようなガレージが課税対象となるのかを見ていきましょう。
ビルトインガレージ
ビルトインガレージとは、住宅の一部として設計されたガレージで、居住空間と一体になっているタイプです。外気分断性、定着性、用途性のすべての条件を満たしているため、固定資産税の課税対象となります。
ただし、ビルトインガレージには固定資産税の軽減措置があり、ガレージの床面積が住宅全体の床面積の1/5以下である場合、固定資産税の計算から除外されることがあります。これにより、固定資産税を抑えることができます。
なお、ビルトインガレージに電動シャッターを設置すると、固定資産税評価額が高くなることがあるので注意が必要です。
コンテナハウス型ガレージ
コンテナハウスを改造したガレージも、外気分断性、定着性、用途性の3条件を満たしていれば、固定資産税の課税対象となります。
ただし、車輪が付いていて移動可能なタイプのコンテナハウスは、定着性がないと判断されるため、固定資産税はかかりません。
一般的なコンテナハウス型ガレージは建築基準法における建築物とみなされるため、建築確認申請や完了検査などの手続きも必要です。これらの手続きを怠ると、違法建築物として罰則を受ける可能性があります。
物置風のガレージ
物置を改造したガレージも、基礎工事を行って地面に固定し、壁やシャッターで外気を遮断する構造であれば、固定資産税の課税対象となります。
反対に、屋根や壁、シャッターがあっても、地面に固定されていなければ定着性がないため、固定資産税はかかりません。
ただし、地面に固定されていないガレージは、強風や台風などで倒壊する危険性があります。安全性を確保するためには、固定資産税がかかっても、基礎工事を行って地面に固定することをおすすめします。
固定資産税がかからないガレージの選び方
固定資産税を抑えたい場合は、3つの条件のいずれかを満たさないガレージを選ぶことが有効です。ここでは、固定資産税がかからないガレージの種類を紹介します。
カーポートの活用
カーポートは、屋根と柱だけで構成された簡易的な車庫です。壁がないため外気分断性の条件を満たさず、固定資産税はかかりません。
カーポートには、Y型カーポート(2本の柱で2台駐車可能)やバルコニー活用型カーポートなど、さまざまなタイプがあります。本格的なガレージに比べて設置費用も安いので、固定資産税がかからない方法として有効です。
ただし、カーポートを設置する際は建ぺい率(土地に対する建物の面積の割合)に注意が必要です。カーポートが建物とみなされる場合、建ぺい率を超えて設置することはできません。
プレハブ小屋の利用法
プレハブ小屋をガレージとして使用する場合、基礎工事を行わず、四隅にコンクリートブロックなどを置いてその上に設置する簡易な方法であれば、定着性がないため固定資産税はかかりません。
ただし、プレハブ小屋は建築基準法では建物とみなされるため、原則として建築確認申請が必要です。地域や使用目的によっては例外もありますが、法的な手続きを遵守することが重要です。
バイクガレージの選択
バイクガレージは、一般的に固定資産税がかからないことが多いです。屋根と柱だけで作られたカーポートタイプや、コンクリートブロックなどの上に置いただけの簡易タイプのバイクガレージは、定着性や外気分断性がないため、固定資産税はかかりません。
ただし、基礎工事を行って地面に固定した場合は、定着性があるため固定資産税の対象となる可能性があります。また、建築基準法において建物に該当する場合は、建築確認申請も必要です。
駐車スペースの有効活用
屋根や壁がない単なる駐車スペースには、外気分断性や定着性がないため、固定資産税はかかりません。住宅の敷地の一部を駐車スペースとして利用する場合、固定資産税の心配はありません。
駐車スペースに屋根と柱を設置してカーポートにした場合も、壁がなければ外気分断性がないため、固定資産税はかかりません。
増築でガレージを作った場合の固定資産税
既存の住宅に増築する形でガレージを作る場合も、外気分断性、定着性、用途性の3条件を満たせば、固定資産税がかかります。
建築基準法において建物に該当するガレージを増築する場合、一般的に10平方メートルを超えると建築確認申請が必要です。必要な手続きを怠ると、建築基準法違反となり、罰則を受けたり、ガレージの撤去命令が出たりする可能性があります。
増築でガレージを作る場合は、事前に自治体の建築課などに相談し、必要な手続きを確認することをおすすめします。
ガレージの固定資産税を安くする方法
ガレージに固定資産税がかかることがわかった場合、少しでも税額を抑える方法を考えましょう。
シンプルな構造を選ぶ
ガレージに電動シャッターやオーバーヘッドドアなどの高価な建具を設置すると、固定資産評価額が高くなり、固定資産税も増加します。機能性や利便性を向上させる設備は資産価値を高めますが、その分税負担も大きくなります。
固定資産税を抑えたい場合は、シンプルな構造のガレージを選ぶことが有効です。必要最低限の機能に絞り、高価な建具や設備を避けることで、固定資産評価額を抑えることができます。
軽量な材料を使用する
ガレージの構造材には、コンクリート、鉄骨、木材などさまざまな種類があります。一般的に、コンクリートや鉄骨などの頑丈な材料を使用すると、固定資産評価額が高くなりやすいです。
固定資産税を抑えたい場合は、軽量な材料(軽量鉄骨や木材など)を使用することで、評価額を下げることができる場合があります。ただし、耐久性や安全性とのバランスを考慮する必要があります。
小規模なガレージにする
ガレージの大きさも固定資産税に影響します。大きなガレージは評価額も高くなり、固定資産税も増加します。必要最低限の大きさにすることで、税負担を抑えることができます。
また、一部の自治体では、床面積が10平方メートル以下の小規模な建物は、固定資産税が課税されない場合があります。自治体によって規定が異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
ガレージを設置する際の注意点
ガレージを設置する際は、固定資産税以外にもいくつかの注意点があります。法律や規制を守り、安全で快適なガレージを作りましょう。
建ぺい率と容積率の確認
建築基準法の建物に該当するガレージを作る際は、建ぺい率と容積率を確認し、法的な制限を超えないようにすることが重要です。建ぺい率は敷地面積に対する建物の面積の割合、容積率は敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合を示します。
これらの制限を超えてガレージを設置すると、違法建築物となり、是正命令や罰則を受ける可能性があります。事前に自治体の建築課などで確認しておきましょう。
消防法の内装制限の確認
ガレージを作る際は、消防法における内装制限も確認する必要があります。内装制限は、火災が発生した場合に炎や煙の拡大を防ぐことを目的としており、内装材料の選定や配置に関する制限が設けられています。
ガレージ内で車両が燃焼するリスクがあるため、内装材料の選定には注意が必要です。特に、ビルトインガレージなど住宅と一体になっているタイプは、厳格な制限が適用される場合があります。
近隣への配慮
ガレージの設置は、近隣住民に影響を与える可能性があります。例えば、ガレージの位置や高さによっては、隣家の日照や風通しを阻害する恐れがあります。また、ガレージの使用に伴う騒音(シャッターの開閉音など)も近隣トラブルの原因となることがあります。
近隣トラブルを避けるためには、事前に計画を説明し、理解を得ることが大切です。また、防音対策や視界確保など、近隣への配慮を行うことも重要です。
建築確認申請の必要性
建築基準法において建物に該当するガレージを作る場合、一般的に建築確認申請が必要です。建築確認申請は、建築計画が建築基準法などの法令に適合しているかを確認する手続きで、工事着工の前に申請・取得する必要があります。
建築確認申請を怠ると、違法建築物となり、工事の中止命令や罰則を受ける可能性があります。ガレージのタイプや規模によって申請の要否は異なるため、事前に確認しておきましょう。
まとめ
ガレージに固定資産税がかかるかどうかは、「外気分断性」「定着性」「用途性」の3条件によって決まります。これらの条件をすべて満たすガレージには固定資産税がかかりますが、いずれかの条件を満たさなければ課税対象外となります。
固定資産税がかかるガレージの代表例は、ビルトインガレージ、コンテナハウス型ガレージ、物置風のガレージ(基礎工事あり)などです。一方、固定資産税がかからないのは、カーポート、簡易なプレハブ小屋、バイクガレージ(基礎工事なし)、単なる駐車スペースなどです。
固定資産税を抑えたい場合は、カーポートなど壁のない簡易な構造を選ぶことが有効です。また、ガレージを設置する際は、建ぺい率や容積率、消防法の内装制限、建築確認申請の必要性なども確認しておくことが大切です。
ガレージの設置は長期的なコストも考慮して計画しましょう。初期費用だけでなく、固定資産税などのランニングコストも含めて検討することで、後悔のない選択ができます。また、法律や規制を守ることで、安全で快適なガレージライフを送ることができます。
住宅展示場に行こうと思っている方や間取りで悩んでいる方へ

注文住宅を検討している方は、「とりあえず住宅展示場へ行ってみようかな?」という方がほとんどです。
しかし、住宅展示場はオススメしません。理由は下記の3つです。
・グレードの高い住宅展示場のモデルハウスは参考にならない。
・大した収穫もなく、資料だけもらって帰ることになる。
また、ハウスメーカーは決まっているけど、間取りに悩んでいるという方へ。他の会社からも間取り提案を無料で受けられるとしたら、魅力的ではないでしょうか?
そこで、オススメするサービスが「タウンライフ家づくり」です。
「タウンライフ家づくり」は完全無料で資料・間取り提案・見積もりがもらえる

「タウンライフ家づくり」は、自宅にいながら全国のハウスメーカーや工務店から提案を受けることができるサービスです。
他にも資料を一括で請求できるサービスはありますが、タウンライフ家づくりが凄いのは、資料だけでなく「間取り提案」「詳細な見積もり」が無料で貰えることです。
累計利用者数は40万人となり、毎月5,000人以上が利用する人気のサービスとなっています。
\簡単・たったの3分/
無料の間取り・見積もり提案はコチラから >
全国1180社以上の加盟店で希望の会社が見つかる
誰もが知っている大手ハウスメーカー27社に加えて、全国のハウスメーカーや工務店など合わせて1180社以上の登録があります。これだけのハウスメーカーや工務店がタウンライフ家づくりに登録していることで、信頼を集める理由となっています。下記はほんの一例です。

また、アンケート調査では、注文住宅部門で3冠を達成しています。

\簡単・たったの3分/
無料の間取り・見積もり提案はコチラから >
依頼は簡単で最短3分の2ステップ
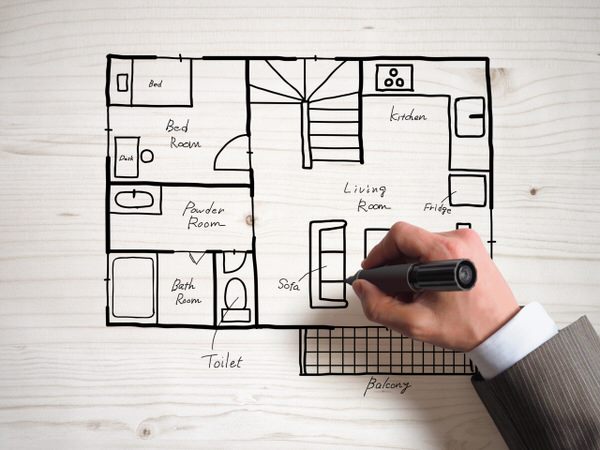
タウンライフ家づくりへの依頼は、とても簡単です。
・希望のハウスメーカー・工務店を選択
\簡単・たったの3分/
無料の間取り・見積もり提案はコチラから >
【PR】
【関連記事はこちら】